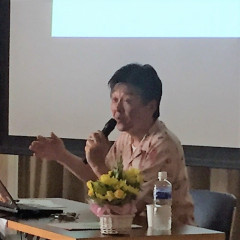15年分の感謝を込めて、次のステップへ♪
理事 下地久美子
7月9日(日)、当NPOが15周年を迎えるにあたり、『家族をとりまく状況は変わったか?15年をふりかえって』をテーマに記念イベントをクレオ大阪中央で開催しました。81名もの方にご参加をいただき、多くの方々に支えていただいていることを実感しました。
第1部は、当NPO理事である団士郎先生のトークライブで幕を開けました。「家族をとりまく道具-モノから見える家族の変化」というタイトルのもと、家族の中に「電話」という道具が入ってきて、家族の関係というものが変化してきたのを、ユーモアたっぷりに、時には辛口の批判を交えながらのトークが展開されました。
昔は、電話のない家も多く、近所の家に借りに行くことがよくありました。一家に一台となってからも、誰が出るかわからないというドキドキ感があり、掛けたい相手が出なかった場合、「どんな風に話すか」に、頭を使って考えたものでした。それが1990年代に入り、携帯電話が普及していったことで、待ち合わせもスムーズになり、GPS機能で子どもの居場所もすぐわかり、便利になった半面、みんなが携帯電話に夢中で、家族が揃っていても、別の人との電話やメールに気を取られ、「体はそこにあるのに、その人はそこにいない」という奇妙な現象を生んでいるというのは、誰もが思い当たることではないでしょうか。
家族の中に利便性の高い道具が入り込んできたことで、家族は何らかの影響を受け、変化しています。それにより想像力が失われたり、交渉する能力が低下していっていると、団先生は指摘します。知らず知らずのうちに緩衝地帯としての家族の機能が消失していっていること、便利さとリスクは背中合わせであることに、気づいていることが大切であるという言葉はとても深いものでした。
トークライブのあとは、パールノートによるピアノ演奏で、参加者のみなさんに、耳にも心にも響く、なごやかなひとときを楽しんでいただきました。
第2部のシンポジウムは、DV子どもプロジェクトとVi-Projectの代表者による15年の歩みをふりかえる発表ではじまりました。ここまで続けてこれたのは、スタッフ同士のチームワークの良さもさることながら、これらの活動の大切さを理解し応援してくださる方々がいたからこそだと、しみじみと思いました。

シンポジストのトップバッターは、当NPO理事で弁護士の石田文三先生で、「親子とは何か-育てない親は吹かない風、流れない川と同じか」というテーマで、民法が親子をどのように定め、最近の裁判所の判断がどう変わってきているか、わかりやすくお話しいただきました。
結婚解消後300日以内に生まれた子どもの父は前夫とされるため、DV被害者女性が出生届を出すことができず、無戸籍の子どもが増えていることは社会問題となっていますが、結局、日本の法律が「結婚」というものをいかに重要視しているかというのは、とても興味深いものでした。
次に、当NPO理事で弁護士の宮地光子先生から、家族の中の「個人の尊厳」に司法はどうかかわってきたかについて熱く語っていただきました。
家庭裁判所の面会交流原則実施論は、裁判所が家父長的意識が強いため、どんな父親でも子どもと面会させるべきというのが強引に推し進められているというのには、誰のための面会なのかと憤りを覚え、家族主義を押し付ける国家の戦略にどう抗っていけばよいか、考えさせられました。
最後は、当NPO理事で臨床心理士の羽下大信先生に「暴力という謎」について、男性の非暴力グループワークを通じて、日々感じることを、笑いを盛り込んで楽しく解説していただきました。
都市の生活は、男性の孤立感や無力感が刺激されやすく、侵入されたと思うと過剰に反撃に出てしまう傾向があり、「負けることは怖くないという敗者の理論」をグループの中で学習していくことで、男性も変わっていくというのには、希望が持てました。
そのあとのディスカッションで、人が成長していくには、横のつながりの中で支え合って学んでいくものという話が出ました。15年の応援に感謝をすると共に、これからもたくさんの方を巻き込み、ゆるやかにつながりを持ちながら、次のステップへ歩みを進めていきたいと気持ちを新たにしました。
参加いただいたみなさまの感想の一部をご紹介します!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆「道具の変化」で家族も変化し、社会全体も個人も影響を受け、それに気づきていることが大切だと教えられた。
◆司法から見た「家族」を初めて知ることができ、子どもの権利や親権について考えさせられました。
◆それぞれの立場の人の話が聞けて有意義でした。このようなイベントを定期的にしていただきたいです。
◆「家族」を市民として、専門家として、支えている人がこんなにおられるのだということに感動しました。
◆モノに振り回され、支配されている日常に、老いも若きも疲れているのを実感しています。
◆同じ風景も見方によって、前進や後退があることを学んだ。
◆普段の生活の中では考えないようなことを考えるきっかけになり、知らないことがたくさんあることに気づき、発見がいっぱいありました。
◆様々なアプローチの違いはあっても、行きつく所は違わないのがこのNPOの良いところだと再認識しました。
(ニュースレター53号/2017年7月)