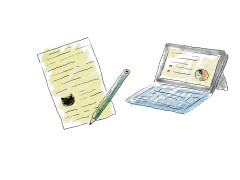小池英梨子
2017年7月当NPOに新しく、「人もねこも一緒に支援プロジェクト」が発足しました。
このプロジェクトは、“ペットを飼育している、支援が必要な個人、または家族に対し、ペットとの切り離しを行わずに多機関が連携して支援を実施する”取り組みを目指しています。
●発足の経緯
プロジェクト代表の小池から発足の経緯や概要など皆様にお伝えさせていただきたいと思います。私は中学生の頃から主に捨て猫の保護活動や、地域のノラ猫問題を排除ではなく共存的に解決していく活動を行ってきました。実際に活動するなかで、猫の問題を解決するためには、猫よりも「人」と関わり、介入や支援を行うことが必要であることを痛感しました。そこで、立命館大大学大学院応用人間科学研究科、対人援助学領域に入学し、当NPO理事長の村本邦子先生をはじめ、理事の中村正先生、団士郎先生がおられる「家族システム・社会臨床クラスター」に所属し、共生と共存社会のリアリティというテーマで自分の活動をベースに修士論文を執筆しました。ここでなぜ、当NPOが「ねこ」とつながったのかご理解いただけたかと思います。
皆さんは「ペットの多頭飼育崩壊」をご存知でしょうか。最近、ニュースでも多く取り上げられるようになってきました。多頭飼育崩壊とは、避妊去勢手術等、適正管理を行わなかったことにより繁殖し、ペットが増え、飼い主が管理しきれない状態に陥っていることを指します。
この写真は今回、人もねこも一緒に支援プロジェクトで支援を行った多頭飼育家庭の様子です。10年ほどかけて3匹だった猫が77頭に増えてしまっていました。生活保護受給世帯のため、ケースワーカーが状況を把握していましたが、「保健所に引き取ってもらってください」という提案以外することができませんでした。外から見ると“増えすぎた猫”ですが、家族にとっては一匹一匹に名前がついている“家族”でした。そのため、家族の行政不信は募り、時間ばかりが過ぎ猫の頭数は増えていく一方でした。
そんな中、福祉事務所から人もねこも一緒に支援プロジェクトに協力の要請がありました。猫への想いと飼育を認めたうえで、現状を改善していくため、ケースワーカー、カウンセラー、人ねこケアPJ(プロジェクト)と当事者家族が協力し、現在は全頭の避妊去勢手術を終え家族と行政との溝は気が付けば埋まっていました。
このように、「ペットも含めた支援をデザインしたら、思ったより人にとっても良いことが多かったぞ。」という展開はきっと沢山あると思います。そういう経験を援助職者方にしていただき、新しい支援の可能性への気付きなどを対人援助職者の界隈にひろげていきたいと思っています。
●人ねこケアPJ(プロジェクト)の目標
・「人が愛着を持っているペットを支援することは、人の生活を支えるヒューマンサービスである。」という理念のもと人と動物が安心して暮らせる社会を目指す。
動物への支援を当事者と協働で行うことによって、当事者の自立支援へつなげていく。
●概要
・ペットを飼育している支援が必要な個人、または家族に対し、ペットと人の切り離しを行わずに、支援を行うプロジェクトである。
・ペットも含め、“家族”として捉え、家族システム論的介入を行う。
・人と動物との関係が危機的状況に陥る前に、支援ができるよう、専門職への知識の啓発共有活動を行う。
・ペットの引き取りを行う保護団体ではない。
●包括的支援の必要性
・切り離しによる部分的支援では対応しきれない。
→子どもだけの支援、母親だけの支援、ゴミだけへのアプローチ、猫だけへのアプローチ、ではなくそれらすべてを含むシステム論的視点が必要である。
・現状への原因や要因は複数存在し、互いに影響しあっており、何か一つに限定することはできない。逆にとらえれば、直接的原因ではないペットへの支援的アプローチを行うことで家族システムが良い方向に動き出すことに可能性に着目し、様々な専門機関と連携してチャンスを逃さないように介入を行う。
●切り離し(殺処分)に反対する理由
・ペットは、飼い主の心の支えである。
→愛着を持っているペットを殺処分されることは、当事者の心に一生涯消えない心の傷と罪悪感をくくりかねない。
・支援者との間に不信感や溝を形成してしまう。
・適正飼育を行えば、臭いの問題は大きく軽減される。
・動物は命あるものである
●適正飼育を支援するメリット
・ペットを適正管理できるようになることで、当事者の自己効力感の向上や、責任感の形成につながる。
・当事者が愛着を持っているペットを大切にすることで、当事者との信頼関係の構築につながる。
・当事者の生きる希望を奪わずに済む。
●活動内容
【個別支援】
ケースワーカー、心理士、弁護士、福祉課や衛生課、愛護センターと連携して人と動物の支援をする。
【啓発】
多頭飼育を未然に防ぐため、援助職者に早期避妊去勢手術の必要性を啓発、実施の支援をする。
【調査】
動物問題の現状調査を行う
●おわりに
動き出したばかりのプロジェクトですが、地道に活動していきますので、応援のほどよろしくお願いいたします!
(ニュースレター53号/2017年7月)
(ニュースレター54号/2018年1月)