5月24日から6月22日までの毎週土曜日、5回連続で「ワーキングマザーのためのストレスマネジメント」がドーンセンターで開かれました。子どもプロジェクトでは、この講習会と並行して、託児所に集まった子ども達を対象に豊かな人間性を育てるプログラムを実施しました。
今回の子プロの活動は、トラウマに関する文献研究やプログラムの企画立案コンペなどを通して温めてきたプログラム案を応用し、実際に子ども達に導入するという初めての試みです。子どもにとって「魅力的でおもしろいプログラム」とはどういうものか、プログラムから子ども達は何を得ることができるのかを実際に学ぶことのできる貴重な機会でした。
託児プログラムでは、各回ごとにテーマを決めた創作活動を行いました。
第1回目はお絵かきとミイラゲーム。お絵かきは、慣れない場所でのプログラムの導入に際して、子ども達にとって受け入れやすいものであり、なおかつ描かれた絵が子ども達の自己紹介のような作品となると考え、取り入れました。ミイラごっこは、トイレットペーパーを子どもの体に巻き付け、その不自由さとそこから解き放たれた開放感を味わうものです。
第2回はお家を作ろう。大きな段ボールを用いて、子ども達の特別な空間作りと折り紙やクレヨンを使って出来上がった家へ装飾を行いました。
第3回はコラージュ。雑誌などの切り抜きをのりで自由に貼っていき、みんなで一緒に大きな模造紙に絵を完成させました。
第4回目はねんどで遊ぼう。色とりどりの小麦粉ねんどを使って、思いを形にすることとねんどの感触を楽しみました。
第5回は変身しようをテーマに、魔法使いやお姫様に変身、子ども達のアイデアからアクセサリーやサングラスも作りました。
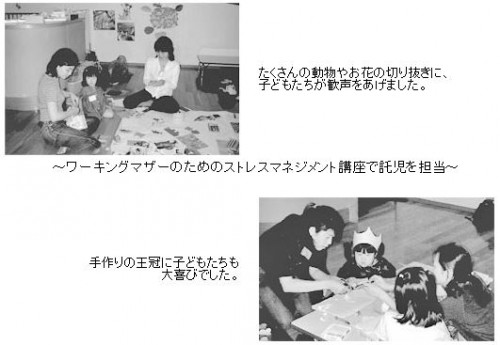
当初は、数個のプログラム案を1回のセッションの中で行う計画を立てていましたが、年齢層も幅広く未就学児が大半だったためプログラム通りにはなかなか進みませんでした。そのため、急きょプログラムを変更して、遊びの導入として上述したテーマを初めに提供し、それ以降は子どもたちが自然につくった流れに沿って、それが発展していくのを見守るといった形をとりました。
このことが功を奏したようで、子どもの内なるエネルギーが力強くあふれる展開が、プログラムの中で数多く見受けられました。そして、日頃味わえないような特別な遊びを経験する中で、子ども達はこれまでにないほど生き生きとした表情を見せてくれました。その様子を垣間見ることができる、子プロメンバーからの報告を一部ご紹介します。
ミイラごっこでは、子どもたちは大喜びでぐるぐる巻きになった後、トイレットペーパーを力一杯引き裂いていました。さらに、ここからがさすが子どもなのですが、びりびりになったトイレットペーパーをお互いに掛け合うという遊びを始めました。
そして、プログラム残り時間10分という段階で片付ける作業を始めたのですが、ここでもさらに子どもの力を見せ付けられました。Aちゃんがゴミをゴミ袋に入れながら、「この中に入りたい」と言い出したのです。Aちゃんがゴミ袋の中に入っているのを見て、ほかの子もまねし始め、結局「人魚さんごっこ」のような形で遊びがどんどんと発展していきました(活動会員)。
家作りでは、年齢の高い子どもはスタッフと共に家を作り、年齢の低い子どもはそれを見てはすすんで飾り作りを手伝っていました。Bちゃんは完成した家の中に、おもちゃのいすを入れ込んだり、託児所にあったおままごと道具を持ち込んだり、机を作ったりして家に工夫を施していました。
そのうちダンボールの小さな家が託児のスタッフと子どもたちでぎゅうぎゅうになってくると、Bちゃんはウレタンを敷き詰めてベットルームを増築するなど見事な創造性を見せてくれました。そのような素敵な空間に引き寄せられて、いつもはなかなかプログラムに参加しにくい子どもも楽しんでいたようです(活動会員)。
このように、子どもたちは自由に遊んでいるうちに内なるエネルギーが活性化し、新たな遊びを自分たちで知らず知らずのうちに創作していくのだということを託児プログラムで学ばせてもらったように思います。そして、今回のプログラムが終わった後、改めて卓上の知識だけでは、プログラム主体のプログラムとなって子どもが置き去りになる危険を孕んでいたことを痛感しました。今後の子どもプロジェクトでは、この経験を生かし、子ども達がプログラムの中で生き生きと、遊びをダイナミックに展開できるような環境作りを忘れずに進めていきたいと思っています。
(ニュースレター第4号/2003年8月)
